公正証書遺言」はなんとなく手間がかかる面倒な方法のように思われがちですが、
実際は必要な書類さえ揃っていれば公証人が作成するので、思ったよりも簡単に作ることができます(ただし一か月ほど時間がかかる)。遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成しますので、様式不備で遺言が無効になる心配はありません。また、遺言の原本は公証役場で保管しますので、自筆証書遺言のように盗難・紛失・第三者による隠匿・変造の心配も要りません。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なのもメリットです。
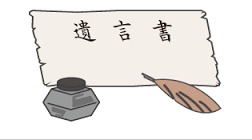
遺言を確実に実行したいと思っている人や、相続手続きで遺族にかける負担を軽減したいしたい人は、ぜひ、検討してほしい方法です。ほかにも次の事柄に該当する人は、自筆証書遺言より公正証書遺言がよいかもしれません。
□相続人がもめそうな財産がある人
□法定相続人以外の第三者に遺贈したい、あるいは寄付をしたい人
□相続人の排除(相続人から除外すること)、婚外子の認知など、法定相続人の
利益を損ねる遺言をしたい人
□高齢、病気やケガで自筆証書遺言が作れない人
□遺言書の保管場所に困っている人
公正証書遺言を作成する際に必要な書類は、以前にも紹介した以下4点などです。
◆遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(または財産をあげる相手・受遺者の住民票)
◆不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
◆固定資産の評価証明書
◆財産目録
これらの書類と遺言者の印鑑証明書を持って、公証役場へ行けば公証人が対応してくれます。
作成する場所はどの公証役場でも構いません。
病気やケガで出かけられない人は、公証人に出張を依頼することもできます。
この場合は自宅の最寄りの公証役場に連絡することです。(※出張費が発生します。)
公正証書遺言作成にあたっては「証人」が必要となります。
この「証人」とは、公正証書遺言を作るにあたり、遺言書の内容や遺言者が本当に自分の意思でその遺言をしているのかを確認する人のことです。
信頼できる友人や親戚に頼むか、もしくは公証役場で紹介してもらうことができます。
ただし、証人は
①未成年者
②法定相続人と受遺者、
③②の配偶者や直系血族
④公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記官や従業員
⑤遺言書の内容を理解できない人
などは証人になれないので注意しましょう。
公証役場を訪ねるときは、前もって電話で確認しておきましょう。
本人が出向けない場合は、家族や第三者に頼むことも可能です。その場合、委任状は必要ありませんが遺言者を特定するために印鑑証明が必要になる場合があるので、
事前の確認を忘れないようにしましょう。
その後、何回かの打ち合わせを重ねたあと、公証人から遺言書の文案を受け取ります。文案は必ずチェックしましょう。
特に人名や地名、数字などは、どうしても間違いやすいものです。
確認したら、公証役場に持参してもいいですし、郵便で返送するか電話やFAXで訂正箇所を伝えても構いません。
遺言書の作成当日は遺言者と公証人、証人が一堂に会します。公証人が、遺言書の文面を読み上げるので、問題がなければ遺言者、公証人、証人の三者が遺言書に署名捺印して完成です。
この時点で変更がある場合は、その旨を明確に伝え、文面の変更を求めて仕切り直します。
公正証書遺言の「原本」は公証役場が保管し、「正本」と「謄本」は遺言者に渡されます。
所定の手数料のほか、証人への報酬を支払ってすべてが完了します。
出張を依頼した場合は手数料の割り増しや交通費などがかかります)。
◆公正証書遺言のデメリット
メリットが多い公正証書遺言ですが、デメリットもあります。
作成には費用がかかること、利害関係のない証人2人の立会いが必要になるなどです。
家族葬 奈良 ESS
