自分を見つめ直して「この先の人生をどう歩むか」整理するためのツール
-エンディングノート-
いきなり、遺言書や委任契約書を作ろうと言われても
尻込みしてしまう人もいるでしょう。
そんな人は「エンディングノート」からはじめることをお勧めします。
事故やアクシデントがあったとき、あるいは人生の終幕に向けて家族に
つたえたいことがあるとき、事前に記入して家族に残しておくノートのことです。
もし、意識が戻らない状況になったときや、突如この世を去るような不幸な事故に
見舞われたときでも、自分の思いを伝えることができます。
これは遺言書ではないので気負って書く必要はありません。
日記を書くのも苦手だという人もいるかもしれませんが、
上手く書こうなどと思わず、家族への感謝の気持ちを残しておくくらいの
気持ちでOKです。
シンプルなものから詳細に記入できるものまで、いろいろなタイプの
エンディングノートが市販されているので、
自分に合ったものを選べばよいでしょう。
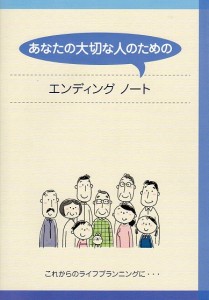
葬儀社がイベントなどで無料で配布していたり、事前相談や
事前見積もりの際にプレゼントしてくれることもあるので、
葬儀社に足を運んでみるのもいいでしょう。
終活アドバイザーやラストライフプランナーがいる葬儀社なら、
記入方法についてもアドバイスしてくれます。
ちなみに弊社(ESS)にはラストライフプランナーが2名在籍しています。
自分の死に際して希望を伝えるための「エンディングノート」を残しておくにしても、
「現実味」がないと墓や葬儀、財産処分をどうするか考えがまとまらず、
書き方に悩むかもしれません。
ある終活アドバイザーは、「過去を振り返り、家族や周りの人とのかかわりを
考えながら自分の立ち位置を確認する『人生の棚卸し』から始めてはどうか」と
提案しています。
エンディングノートはいわば、自分の生きた証しです。
家族にとっては、あなたの思い出をいつまでも残しておく記念になります。
これは家族への最高のプレゼントになるでしょう。
さらにエンディングノートを用意しておけば、万一のとき、家族を悩ませる負担を
軽減できるというメリットがあります。
エンディングノートには、葬儀のことや介護についてなどの
細かな項目まであります。
例えば重病の時、病名や余命宣告の告知をするべきかどうか、
あるいは自分の判断能力が低下した時、誰に介護を頼みたいか、
どのような介護を望んでいるのか、また回復の見込みがない末期症状のとき
延命措置を行うのか、財産の管理はどうするのか、さらに望む葬儀の希望を
内容を書いておけば、家族を迷わせずにすむし、
心理的負担は軽くなるはずです。
このように、エンディングノートは、自分の生きた証しを残せるのと同時に
、家族の負担軽減の手助けをしてくれるアイテムなのです。
エンディングノートに着手したら、内容は毎年見直してほしいと言われています。
なぜなら1年過ぎれば生活環境や考え方は変わるもので、
要望事項もそれに応じて変化する可能性があるためです。
次回はエンディングノートの書き方と注意点について説明します。
